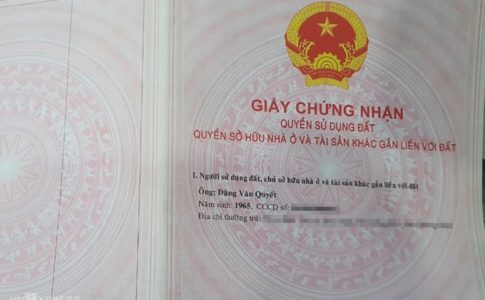ベトナムは、約40年にわたる「ドイモイ(刷新)政策」により、経済・社会の多方面で目覚ましい成果を上げてきた。世界の多くの国々と比較した際の所得格差も大幅に縮小している。
ドイモイ政策の始動と困難
1986年に中央集権的計画経済から市場経済(社会主義市場経済)への移行を開始したベトナムは、長期の戦争や国際制裁、極度の経済困難に直面していた。特に初年度のインフレ率は774%と凄まじく、数年間にわたる物価抑制政策が必要だった。1993年にはインフレ率を一桁台に抑制することができ、1993年~2000年は5%前後で安定させた。
貧困削減の飛躍的成果
市場経済の導入により、農業から工業、流通まで経済活動が活性化したが、1990年の一人当たりの年間所得は100ドル未満、人口の70%が貧困状態にあった。1993年にはこれが58%まで改善され、現在では**多次元貧困基準** で1.9%未満にまで減少している。この基準は、所得だけでなく教育・保健・生活環境など複数の指標を総合して生活の質を評価する方法であり、単なる所得だけの貧困率よりも、国民の実際の生活水準をより正確に反映する指標とされている。
所得格差の劇的な縮小
2000年以降、ベトナムの一人当たりGDPは周辺地域および世界各国との格差を大幅に縮小した。例えば、2000年にはシンガポールとの格差は55.8倍であったが、2024年には19.7倍にまで縮まった。タイとは5.2倍から1.6倍、マレーシアとは9.6倍から2.7倍に格差が縮まり、インドネシア、フィリピン、インドに至っては追いつき、追い越す勢いである。
社会主義市場経済モデルの優位性
ベトナムの急速な追い上げは、政治的安定を背景にした社会主義市場経済モデルの有効性を証明している。市場経済の制度を整えつつ、政府がリスク管理や社会保障を行うこのモデルは、単なる混合経済ではなく、制度的に市場経済が機能する基盤を持っている。
経済規模と所得水準
ベトナムは2009年以降、中所得国に分類されているが、実質購買力(PPP)ベースで見れば既に高所得国に近い水準であるとされている。実際、ベトナム経済には統計上のGDPやGNIでは把握しきれない部分もある。たとえば、正式な統計には含まれない小規模事業や自営業、デジタル経済など、合法的でありながら従来の統計手法では完全に計上されていない経済活動が存在する。このため、実際の経済規模や市民の生活水準は、統計上の数字よりも高い可能性がある。
経済成長の全体像
1945年の独立以降、1975年の統一、1986年の改革を経て、ベトナムは戦争の荒廃から地域経済の主要国へと成長した。所得格差の縮小は世界の経済機関の予測を超える成果であり、今後も持続的な成長が期待される。
※本記事は、各ニュースソースを参考に独自に編集・作成しています。
ベトナム進出支援LAI VIEN