専門商社のベトナム再挑戦
顧客が異なるゴムと化学品
ベトナム進出から約50年。1973年という激動の時代に産声を上げた三洋貿易のベトナム事業が、今まさに「再挑戦」の時を迎えています。
同社が展開するのは、日系企業への安定供給を担う「ゴム事業」と、熾烈な価格競争が展開されるローカル市場を射抜く「化学品事業」の二極戦略。一見すると相反するこの二つの市場を、いかにして専門商社ならではの知見で繋ぎ、成長へと変えているのか。
SANYO TRADING (VIET NAM) の弥武正哉社長に、現地スタッフによる新規開拓の舞台裏から、農業廃棄物を資源に変えるサステナブルな輸出構想、そしてさらなる飛躍を見据えたM&Aの展望まで、じっくりとお話を伺いました。

1973年の進出から現地法人設立までの軌跡|「インドシナ室」から始まった商社の歩み
―― 三洋貿易さんの事業を教えてください。
弥武 専門商社として海外から輸入した製品を日本国内で販売するのが主事業です。分野は主に5つありまして、1つはゴム事業で、合成ゴムやゴム部品等に使われる各種原料を取り扱っています。次は化学品事業で、塗料、インキ、接着剤、プラスチックなどのメーカーに化学原料を販売しています。
3つ目がグリーンテクノロジー事業で、木質ペレットのミル(成型機)や木質バイオマスの加工機などのマシンを扱っています。4つ目は自動車関係のモビリティ事業で、シート周りの部材が多く、座席暖房装置のシートヒーターや乗員の腰の部分を支持するランバーサポートなどの製品です。
最後がライフサイエンス事業で、研究室で使用される小型の分析装置や試験機、化粧品原料や食品添加物、環境対応型フィルムなどを扱っています。
海外は、米国、メキシコ、ヨーロッパ(ドイツ)の他はアジアが多く、我々のベトナム、中国、韓国、シンガポール、タイ、インドネシア、インドに拠点があります。
海外拠点は日本向けの輸出ではなく、各拠点が輸入した製品を各国内で販売しています。つまり日本と同じ業態でして、ベトナムも同様です。

―― ベトナム進出の経緯を教えてください。
弥武 進出は早くて1973年です。当時は「インドシナ室」と呼ばれていたようで、ベトナムで伐採した木材の日本への輸出がメインでした。ただ、黒字化がなかなか難しく、その後は三洋貿易の祖業であるゴムを扱うようになりました。
商社の現地法人は認可が難しかったようで、駐在員事務所のまま続いて、現地法人のSANYO TRADING (VIET NAM)を設立したのが2010年です。ここから本格的に事業を始めて、現在はゴム事業部、私の出身である化学品事業部、ライフサイエンス事業部の3部門があります。事業の規模は3つとも同程度です。

ゴムは主に当地の日系のゴム関連会社さんやゴムの部品メーカーさんに、合成ゴムやゴムの原料を販売しています。化学品は逆で、ローカルの塗料メーカーさんやプラスチックメーカーさんに各種原料を販売しています。
ライフサイエンスは化学品事業部から数年前に枝分かれした部署で、排水処理用などの水処理材の販売と、少し変わった事業ではベトナムやラオスの鉱物を日本に輸出しています。そのため、大きくはゴムと化学品の2つが主たる事業になります。
―― その2つはどのような仕事ですか?
弥武 ゴム事業の海外展開は、日本でお取引のある自動車部品メーカーさんなどの進出をきっかけに、我々も同じ国に進出して、現地でゴムの供給を始めることが多いです。ベトナムも同様でして、そのためお客様はほとんど日系企業です。
自動車部品を例にすると、自動車メーカーが決めた原料が世界共通になることが多いです。海外でも日本と同じゴム原料などが使われることがあり、安定供給に努めています。

化学品は全く違います。ベトナムには化学品のローカルメーカーが少なく、化学原料の国内調達は難しいため、基礎的な原料からほとんどを輸入に頼っています。そこで弊社のベトナム人スタッフがご要望に応える輸入原料を提案するなどして、顧客を新規開拓しました。
顧客は日本と同じく塗料、インキ、プラスチックなどのメーカーさんですが、ローカル企業とグローバルの外資系大手企業が比較的多くなっています
塗料を例にしますと、日系の塗料メーカーさんも進出されていますが、ローカル企業が使う原料は日本と異なります。その理由は日本に比べた価格競争の激しさで、日本ではある程度高額でも機能性を重視する傾向がある一方、ベトナムはそのケースは稀です。
例えば家屋の外壁の塗料です。日本では10年保証や20年保証があって、耐用年数を延ばす高機能素材が使われていますが、ベトナムではその需要がまだ高くないように思います。
そのため高機能品の販売先は、最終的に欧州や米国に輸出する製品向けになります。一定の納入量になっていて、ビジネスチャンスともとらえています。

【今後の3大戦略】売上倍増、サステナブル輸出、そしてM&Aへの展望
―― 御社の強みとは何でしょうか?
弥武 化学品を扱う企業は日系、外資系、ローカルもありますが、弊社のスタッフは基本的に英語を話しますし、海外からの仕入れなどのやり取りは問題ありません。
また、日本で輸入した商品をベトナムで展開できることも大きいです。日本の仕入先にはベトナムに代理店を持たない企業もありますから、弊社の話をすると乗っていただけて、ベトナムで販売することも多いです。
ローカル企業の特性も影響していると思います。何らかのメリットがある商品を持っていくと、すぐに
テストして、結果的に購入いただくことがあります。日本で原料を変えるにはその企業の顧客などからヒアリングが必要となるなど、早期の切替えは時間が掛かることが多いです。
特にオーナー企業ではテスト後に即購入となるケースもありますが、逆に言えば弊社も顧客を取られる可能性があり、安心はできないです(笑)。

―― 今後の予定や計画を教えてください。
弥武 ベトナムの市場は大きくも小さくもないと思います。それでも1億人の人口で経済成長が著しく、化学原料の需要は増加していくと思います。また、将来的には国内向けに高機能素材が使われるようになるでしょう。
その意味でまず事業規模を増やすのが使命です。今は日本人駐在員が3人で、ベトナム人スタッフはホーチミン市に10人、ハノイに4人(取材時)。この17人の体制から私が帰任するまでに、売上を2倍にしたいです。
もう一つは、ベトナムからの輸出をやっていきたいです。農業の廃棄物の中から化学原料を取り出して、欧州へ送るなどです。近年では石油化学が避けられて、自然でサステナブルな製品が欧州を中心に好まれています。リサイクルにもなります。
ベトナムでは今後も地場の化学メーカーは育ちにくいでしょうし、逆に1次産業の割合は他国と比べて大きいので、農業から化学品の元を取り出すビジネスは有望と感じます。
最後に、三洋貿易は積極的にM&Aを続けており、この数年は毎年のように企業買収をしています。ベトナムでも3事業部と提携できるなら、ローカル企業とのM&Aを模索したいと思います。








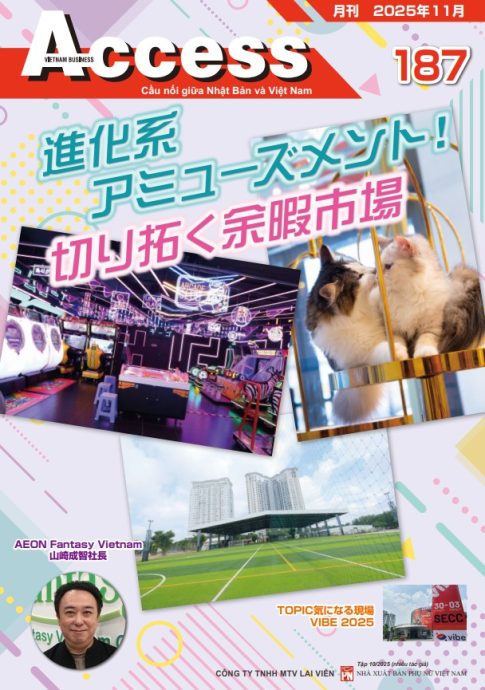












取材・執筆:高橋正志(ACCESS編集長)
ベトナム在住11年。日本とベトナムで約25年の編集者とライターの経験を持つ。
専門はビジネス全般。